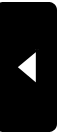ストロベリークライシス
2019年04月28日 18:38 by igoten │Comments(2) │その他
今年は4月中旬は温かく、イチゴの花が一斉に咲いた。
しかし、「好事魔多し」の言葉通り、この寒さである。
今日の朝恐る恐る見たら、まさに満開のイチゴの花は、ことごとく花芯が黒く変色して壊死しているではないか。
2~3日前までは、夢見る甘い畑が、累々たる花の死骸で覆い尽くされている。
被害はイチゴだけではない、30cm程に伸びたウドは真中から折れるように垂れ下がっている。
更に、新しく出てきたキュウイの葉は、殆どがしおれてしまった。
驚いたことに、柿の新芽もほとんどは萎れている。
こうなるともう、植物の自然の回復力を待つしかない。
どうなることやら。
パリは燃えているか
2019年04月26日 15:40 by igoten │Comments(2) │その他
石の建物なのになぜ燃えるのか、と思っていたら、屋根が木製だったんですね。
それとパリに真ん中になぜダムが在るかと不思議に思っていましたが、DAMEは貴婦人という意味だったんですね。
そういえば、ドイツで公衆トイレに入ろうと思ったら、「Damen」「Herren」と書いてあって、どちらが男性用で、 どちらが女性用か判断がつきませんでした。
「Damen」はDameの複数形で、こちらが女性用と後で知りました。
ノートルダムは2回ほど行っていますが、ヨーロッパはどこの都市に行っても大きな協会に案内されて、 もううんざりしていたので、どこに行っても下を見て歩いていたような気がします。
ノートルダムには巨大なパイプオルガンがあったんですね、これも知りませんでした。
「少しのことにも、先達はあらまほしき事なり」と兼好法師も言っています。
今となっては手遅れですが。
よく眠れる音楽
2019年04月24日 15:37 by igoten │Comments(4) │その他
「良く眠れる音楽」という謳い文句の音楽がたくさんありますが、どれもこれもあまり効果は無いようです。
音楽よりもむしろ、「雨の音」「波の音」「水の流れる音」などの音系(音楽系ではなく単なる音)が効果があるようです。
「草原を渡る風」なんてのはかなり効果的のように思いますが、視覚的には見えますが、残念ながら音がしません。
音系が良くても、長らく聞いているとその音に慣れてしまします。
そこで最近私は、「メンデルスゾーンのバイオリン協奏曲」いわゆる「メンコン」というのを聞いています。
これは効き(聞き)ますね、枕元の左右のスピーカーを置いて、バイオリンがどのへんにいるのか、バイオリンの 弓がどのように動いているのかそれだけに集中します。
間違ってもメロディを追ってはいけません。
運が良ければこれで眠りに落ちます。
メンコンといえばやはりこの人、「ヒラリー ハーン」
2,000万回以上の視聴があります。
運が悪いときは、ヤケクソで、ハードロックなんかをかけます。
これはこれで、聞き終えるとぐったりして眠りにおちる場合があります。
知る人ぞ知る、スージー・クアトロの「ワイルド・ワン」
音楽よりもむしろ、「雨の音」「波の音」「水の流れる音」などの音系(音楽系ではなく単なる音)が効果があるようです。
「草原を渡る風」なんてのはかなり効果的のように思いますが、視覚的には見えますが、残念ながら音がしません。
音系が良くても、長らく聞いているとその音に慣れてしまします。
そこで最近私は、「メンデルスゾーンのバイオリン協奏曲」いわゆる「メンコン」というのを聞いています。
これは効き(聞き)ますね、枕元の左右のスピーカーを置いて、バイオリンがどのへんにいるのか、バイオリンの 弓がどのように動いているのかそれだけに集中します。
間違ってもメロディを追ってはいけません。
運が良ければこれで眠りに落ちます。
メンコンといえばやはりこの人、「ヒラリー ハーン」
2,000万回以上の視聴があります。
運が悪いときは、ヤケクソで、ハードロックなんかをかけます。
これはこれで、聞き終えるとぐったりして眠りにおちる場合があります。
知る人ぞ知る、スージー・クアトロの「ワイルド・ワン」
信州型不眠症
2019年04月23日 09:47 by igoten │Comments(2) │その他
およそ、4月の終わりから7月の中頃まで、夜よく眠れないのである。
漢字の4字熟語に「輾転反側」(てんてんはんそく)なる言葉があるが、まさに言いえて妙だ。
万葉集からとった言葉、「令和」などと言って日本人は浮かれているが、中国の文化を見ると、 日本の文化などその足元にも及ばないのかもしれない。
現在、漢字という素晴らしい文化を中国は半分捨ててしまったが、その愚行についてはさておき、本題の不眠症に戻る。
この病は患ったことが無い人には、到底その苦しさは理解できないだろう。
「眠くならないなんて、素晴らしいではないか」と人は言うかもしれないが、不眠症は、眠くならない病ではなく、眠れない病である。
即ち、眠れないから年がら年中眠いのである。
「全てのものは波動である」とアインシュタインは説いた。(そんなことは説いてないか。)
いずれにしろ眠気というのは、波である。
眠気が少し和らいで安心していると次に猛烈な眠気が襲ってくる。
そしてこの睡魔との戦いは、イエスキリストの「荒野の誘惑」に比するほど、過酷である。
キリストは「人はパンのみに生きるにあらず、悪魔よされ!」と言って悪魔を退けたが(ちょと違うかもしれない)、私の場合「人は睡眠のみのに生きるにあらず、睡魔よ去れ!」といえども、一向に睡魔は去らず、ますます私を睡眠に引き込もうと画策する。
さらば、「寝てしまえ」と居直って寝ようとすると、再びあの4字熟語が現れ私の眠りへのいざないを妨害するのである。
人間ドックの時だけ年に一回会う女医さんに、「これこれこういう事情の不眠症です」とアドバイスを求めたが、先生はしばらく 考えていて、それは「信州型不眠症ですね」とのたまった。先生がしばらく黙っていたのは、私の病の治療法を思案していた のではなく、なにか気の利いた病名を考えていたのである。
良い病名が思いついたので、先生も患者もホット一息つき、その話はそれきりとなった。
さて問題は下のyutubeの動画であるが、この動画と不眠症と関係は、今日は眠いので次回説明することにする。
ソフト工房波田
2019年04月03日 09:53 by igoten │Comments(0) │その他
ガラ紡機とは
2018年09月17日 09:27 by igoten │Comments(0) │臥雲辰致とガラ紡機

(現存するガラ紡機)
ガラ紡機とは
ガラ紡機は、臥雲辰致により明治時代に考案された紡績機でそのガラガラという騒音から、ガラ紡と呼ばれた。
紡績とは主に綿や羊毛、麻などの短繊維を非常に長い糸にする工程を言い、特に綿を使った紡績のことを綿紡績と言い、出来上がった糸を綿糸と言う。
間違いやすいので書いておくが、長繊維の絹を蚕の繭から繰り出し、ばらばらにならないよう数本まとめて撚る工程を製糸と呼ぶ。
(注1)化学繊維を作ることを紡糸と言う。
ガラ紡機が果たした歴史的な役割
臥雲辰致と言う名前は知らなくても、江戸末期から明治の初期にかけて欧米と結んだ不平等条約により、金などの貴重な日本の財産が海外に流出したことを知っている人は多いだろう。
江戸幕府が、1858年アメリカと結んだ日米修好通商条約の一般品の課税率は20%で、当時としては極めてリーゾナブル(適当)な税額であり、これに関しては不平等とは言えなかったが、 文久3年(1863年)5月、長州攘夷派の久坂玄瑞らがアメリカ商船ペンブローク号を馬韓海峡で砲撃する。
これに対して、アメリカ、フランスは圧倒的な火力を以て、長州に報復し、長州は手痛い打撃をこうむる。
戦闘で惨敗を喫した長州藩は講和使節の使者に高杉晋作を任じたという話は有名な話で、一度は聞いたことがある人は多い。
結局、この戦争の賠償は江戸幕府が行うことになるのだが、その額が高額で幕府でも支払いきれない。
その結果が、輸入関税の実質的な引き下げである。
それまで、輸入関税は、輸入品価格の35%ないし5%をかける従価税方式であった関税が、4年間の物価平均で定まる原価の一律5%を基準とする従量税方式に改められた。(「改税約書」1866年6月25日)
これは当時の物価上昇を考慮に入れると、ほぼ無税に近いものであった。
これにより、100年余り先行して産業革命が始まったイギリスから安価な綿糸、綿織物が大量に輸入され、我が国在来の手工業的な綿業は壊滅的な打撃を蒙るのである。
大正14年の東洋経済新報社「大日本外国貿易五十六年対照表」によると日本の貿易収支は、明治初年度は輸出総額が1,553万円に対し輸入総額1,069万円で483万円の黒字で有ったが、翌明治2年は輸出総額1,291万円、輸入総額2,078万円となり787万円の赤字に転落する。
その後の貿易収支は明治9年に若干の黒字を記録するが、明治14年まで赤字体制が続くのである。
明治初年度の総輸入額は1,064万円であるが、輸入金額は十年後には2.7倍に膨れ上がり、総輸入額に対する綿製品の輸入比率は36%余りであった。
この貿易収支の赤字を放置すれば、やがて日本は独立国家としての存続の危機に瀕することは明白であった。
治政府は輸入防遏(ぼうあつ)・殖産興業の展開をもってこれに対抗し2,000錘紡績機を輸入して、官営の愛知紡績所と広島紡績所を建設し、紡績工業の育成を目指した。
一方で、政府は起業公債基金で2,000錘紡績機10基を輸入し、民間に無利息10年賦で払い下げた。
また政府の輸入代金の立替払いという保護で、紡績所が設立され、これらの2,000錘紡績機を基本とする模範勧奨工場が、明治10年代の殖産興業の中心となるのである。
しかし政府のもくろみは、2,000錘の規模の小ささ、経営・技術上の未熟と、水力の不安定性、国産原料綿の不適性、立地条件の不利などの原因により失敗に終わる。
(飛び杼)
しかしここに救世主が現れる、それは飛杼(とびひ)である。
飛杼はイギリス人ジョン・ケイによって発明されイギリスの産業革命のきっかけになった発明ともいわれる。
飛び杼は日本に明治6年、フランスに留学していた京都・西陣の織工、佐倉常七によってもたらされた。
この飛杼により手織り織機の作業能率は3倍以上になり、問屋制家内工業での綿織物業は生産性が向上し、国内の殆ど壊滅状態だった、綿織物業の回復を見る。
そして国内綿産業の回復により、更なる安価な国産の原料綿糸の生産が望まれるようになる。
そんな時、まるで彗星のよう、ガラ紡機が出現する。
ガラ紡機は西洋方式とは全く異なる方式で、安価な原料綿糸の生産を可能にし、短時間のうちに全国に広がっていく。
村瀬正章はその著書「臥雲辰致」の中で次のように書いている。
「明治九年当時我が国の様式紡績機は、紡錘六千、織機百台、ただこれだけであったが、この時に構造軽易・操作簡便な臥雲機の出現は、まさに干天に雲霧を望むようなものであり、たちまちにして全国に普及し、わが国綿業史上に果たした役割は極めて高く評価されるべきものである。」
すなわち明治政府が行った「官制模範工場」の政策が失敗する間に、全国に造られたガラ紡機を使った紡績工場は、安価な和紡糸を供給し増加する輸入紡糸の防遏の一助となる。
明治15年、渋沢栄一らの主唱で、大阪に近代的設備を備えた大阪紡績会社(現・東洋紡)が設立され、蒸気機関による本格的な綿糸の機械制生産が始まると、これが刺激となり、明治19年から明治25年にかけて、三重紡績、天満紡績鐘淵紡績、倉敷紡績、摂津紡績、尼崎紡績など20に及ぶ紡績会社が次々と設立され、それに押されガラ紡は衰退するが、大阪は「東洋のマンチェスター」とよばれるようになり、明治23年に国内綿糸生産高が綿糸輸入高を上回り、その後、日本は世界最大の紡績大国に成長し、綿糸紡績業は日本の主要な輸出産業となった。
最終的には品質コストがまさる西欧の紡織機に取って変わられることになるのであるが、明治時代の日本にとって一番大切な時期に、ガラ紡機が果たした役割は極めて大きといえる。
「臥雲辰致の研究」
「臥雲辰致の研究」
2018年09月17日 08:12 by igoten │Comments(0) │その他│臥雲辰致とガラ紡機

(臥雲辰致)

(明治10年代第一回内国勧業博覧会で鳳紋賞牌-最高の賞を授与された”ガラ紡機”)
明治の初めに、西洋の技術によらない紡績機(綿から糸を作る機械)を発明した
天才発明家、臥雲辰致について下のホームページに記載しています。
興味のある方はご覧ください。
「臥雲辰致の研究」
動くべきか、否か
2018年02月09日 09:19 by igoten │Comments(4) │その他
昨日は松本発6:51のスーパーあずさで出張。
スーパーあずさは新車両になってなかなか座り心地が良くなった。
ランバーサポートというか、腰のあたりを後ろから押すような
シートの構造になり、長時間座っていても疲れにくくなった気がする。
100V AC の電源コンセントが前の座席の後ろの下に付いて、
PCなどに充電できるようになった。
私はもっぱらあずさは寝室と考えているので、電源コンセントは
無関係なのだが、使っている人もそこそこいる。
最近は列車内で寝るときはマスクをすることにしている。
大きな口を開けて寝ているところを人に見られないので、
安心して口を開けて寝ることが出来る。
マスクをするというのは何か、カーテンの陰から外を窺っているような、
覗き趣味の快感がある。
こちらの表情を人には見せずに、人の表情を盗み見ているのだ。
ただし周りの人の殆どがマスク着用だと、皆がカーテンの陰から
覗き見ているような、なんだか変な状況になるのだが。
あずさが相模湖駅に到着した時に、社内の放送があり、阿佐ヶ谷駅で
人身事故が発生しその周りの列車が一斉に停車しているという。
その後再度放送があり、相模湖から臨時列車が高尾駅に向かって
出るので、新宿方面に行く人はそれに乗車して高尾駅で京王線
に乗り換え、新宿駅を目指すことを推奨するという。
私が行きたいところは荻窪で、新宿まで行ってまた戻る必要がある。
新宿から荻窪は、中央線を使わずに地下鉄丸の内線で行くことも
出来る。その後何回も社内放送があり、相模湖から列車を乗り換え
高尾から京王線に乗り換えることを勧めている。
こういう時はどうしたら良いんでしょうね、このままアズサが動き出す
のを待つか、乗り換えるか。迷った挙句私は動かないことに決めた。
結果的には約1時間遅れで荻窪に到着し、何とか会議に間に合ったが、
列車を乗り換えたら、更に30分以上かかったと思われる。
高速で事故渋滞にあったとき降りる方が良いか、待つほうが良いか?
バタバタ動くより、状況に任せる方がよい場合が多い気がする。
Deep Learning-4
2018年02月01日 09:53 by igoten │Comments(3) │Deep Learning

筒井康隆のSF短編に「メタモルフォセス群島」というのがある。
この本を読んで私は初めて”多態性”という言葉を知った。
”多態性”はポリモーフィズムと訳される。
”冬虫夏草”という植物があり、漢方薬として珍重されて
いるが、この”冬虫夏草”は、冬は昆虫で夏は草になるという。
まさに、多態性そのものである。
残念なことは、実はこの”冬虫夏草”は冬眠した幼虫に草が寄生した
だけだったと判明した。
しかし、環境によりオスになったりメスになったりする動物は実際に
存在する。
さて、Pythonであるが、驚いたことに、徹底したポリモーフィズムが
行われる。
>>> s = 5
>>> s * 5
10
>>> s = "morning"
>>> s * 3
'morningmorningmorning'
sのタイプによって「*」が多態化する。
Deep Learning-3
2018年01月30日 15:16 by igoten │Comments(2) │Deep Learning
なんとも奥深い言葉であろうか。
これは、LearningがDeepなのであろうか、それともDeepをLearningするのであろうか。
まさか、DeepがLearningするのではないでしょうが。
「He saw a woman in the garden with a telescope.」
という英語があるが、普通は「彼は、望遠鏡で庭にいる婦人を見た」と訳す。
しかし「彼は、庭にいて望遠鏡で婦人を見た」と訳すこともできるし、
「彼は、庭にいて望遠鏡を持った夫人を見た」とも訳せる。
などと考えながら、先ずはプログラミング言語「Python」をインストールする。
「Python」は今最も注目されているプログラミング言語である。
AIで使われる「Deep Learning」は「Python」で書かれることが多い。 その理由はDeep Learningで使用される「ニューラル・ネットワーク」といわれる 人間の脳を模した計算式が、行列式で表され、なんとPythonは行列式の計算が 得意なのである。
私は、「Deep Learning」も「Python」も全く初めて、この年にして両方を同時挑戦する。
参考書は、上の画像の本「ゼロから作る Deep Learning」である。
先ずは、Pythonのインストールから始める。PCはWindows10である。
Pythonは「ニシキヘビ」のことらしいが、このPythonを単独でインストールしても 良いのだが、「Anaconda」と言うインストーラーが存在する。(正式にはディストリビューションというらしいのだが。) Anakondaを使えばDeep Learningに使用するPythsonのライブラリーも一緒にインストール されると本にあります。
Anaconda3 ダウンロード
から「Python 3.6 version 」をダウンロードしてインストールすればOKである。
インストールのフォルダーであるが、私は面倒なので「c:」直下に置きました。
念のために、python.exeのパスを通しておきます。
Windows10ではパスの通し方が面倒です。
コントロール パネル > システムとセキュリティー > システム
とたどって行って左側のリストにある「システムの詳細設定」をクリックすると、 「システムのプロパティ」のウィンドウが現れるので、その下から二番目の行の 「環境変数(N)...」をクリックして、「環境変数」の中の「システム環境変数(S)」の 「Path」を選択し「編集...」ボタンを押して現れる、リストの一番下に、
「C:\Anaconda3」と書いて、「OK」ボタンを押します。
「C:\」直下以外の場所にインストールした場合は、そのパスを入れればOKです。
これでPythonのパスが通ったので、コマンド・プロンプトプロンプトで「Python」と 入れれば、Pythonのプロンプトン「>>>」がでて、Pythonが始まります.