村上春樹
 若い読者のための短編小説案内
若い読者のための短編小説案内 村上春樹 (著)
「BOOK」データベースより
戦後日本の代表的な作家六人の短編小説を、村上春樹さんがまったく新しい視点から読み解く画期的な試みです。 「吉行淳之介の不器用さの魅力」「安岡章太郎の作為について」 「丸谷才一と変身術」…。自らの創作の秘訣も明かしながら論じる刺激いっぱいの読書案内。
戦後日本の代表的な作家六人の短編小説を、村上春樹さんがまったく新しい視点から読み解く画期的な試みです。 「吉行淳之介の不器用さの魅力」「安岡章太郎の作為について」 「丸谷才一と変身術」…。自らの創作の秘訣も明かしながら論じる刺激いっぱいの読書案内。
最初に申し上げるがこの本は相当に難解である。
正直に言うと私はこれまで村上春樹という作家の本をほとんど
読んだことがない。
理由は特にないのであるが、強いてあげれば「海辺のカフカ」が
あまり面白いと感じなかったので、その後触手が伸びなかった
のかもしれない。
もしこれからこの本をこれから買おうとする方は、476円+税
をどぶに捨てたつもりで購入するか、あるいは何事があっても
最後まで読みぬくぞを言う強い覚悟で臨むか、いずれかの
心構えが必要である。
私のようにちょっと手に触れたのをいいことにこの本を
購入した者は、5分と読まないうちに本を後ろに投げ出して
テレビをつけたり、深いため息をついて布団をかぶって
寝てしまうはめになる。
そして挙句の果て、村上春樹が羊に乗って追いかけてくる夢を
見るのだ。
斜めに読んだり下から読んだり、挙句の果て本を後ろから読むような
私にとって、このような本は最も苦手な部類に入る。
つまりこの本を読む時は書かれた語句を、一つ一つ確認しながら
頭の中に並べていかないと、同じ個所を何回も読む循環地獄に
陥る。
とりあえずひいひい言いながらどうにか読み切った。
しかしまったく救いが無かった訳でもない、この本の中の
小島信夫の「馬」を読みながら私は、そのおかしさの為に笑ころげ
しかも村上春樹の解説を読みながら、この小説家のとてつもない
知恵にただただ恐れ入ったのである。
村上春樹少し読んでみようかな。
[後日 記]
この本は素晴らしい本であることがわかった。
今は座右の書である
2009年05月30日 Posted by igoten at 07:45 │Comments(2) │読書
父の詫び状-2
 父の詫び状
父の詫び状 向田 邦子 (著)
「BOOK」データベースより
度鳴る父、威張る父、殴る父、そして陰ではやさしい心遣いをする父、 誰でも思い当たる父親のいる情景を爽やかなユーモアを交えて描き、 名人真打ちと絶賛された著者の第一エッセイ集。
度鳴る父、威張る父、殴る父、そして陰ではやさしい心遣いをする父、 誰でも思い当たる父親のいる情景を爽やかなユーモアを交えて描き、 名人真打ちと絶賛された著者の第一エッセイ集。
このエッセイ、一度読み始めたのであるが、1~2編を読んで止めて
しまったものを、改めて読み直してみた。
結論から言うと秀作であった、ユーモアのある独特の語り口は秀逸である。
最近私は風呂に入るとき必ず何かの短編集を持って入ることにしている。
そのおかげで超カラスの行水であった入浴時間が人並みとなった。
この本を読み出したら面白くて、風呂で読むのは一日一編までと決めた
禁を破って2編読んだほどである。
次は「わが拾遺集」の中の一説である。
父は几帳面なたちで、物を忘れたり落としたりということの ない人であったが、一度だけ、夜明けの玄関で、背広のポケットを 押さえて、「あれ、月給袋、どうしたかな」といったことがある。
出迎えた母は、いつもはゆっくりとした口を利く人が、この時は 黒柳徹子嬢も顔負けの早口で、
「車ですか」
と噛みつくようにたずね、ボオッとして立っている父を突き飛ばして 転げるように表へ飛び出した。
玄関から門まで五メートル、その先に二十メートルばかりを足袋裸足で 走り、発車したばかりのタクシーに追いすがって呼び止め、車中を くまなく点検した。
月給袋は父の思い違いで別のポケットに入っていたのだが、若いころから 俊足を誇り自分の名前の敏雄を説明する時、「機敏の敏」などと得意に なっていた父は、母に突き飛ばされたまま呆然と玄関に立っており、 日頃は、愚図だ、のろまだと父に怒られていた母が誰よりも早く飛び出した のである。
......
しばらくの間我が家では「お母さんのマラソン」が食卓の話題になり、
その話になると父は新聞を広げて顔をかくして読みふけるフリをしていた ようであった。
なかなか良い一節ではないか。
さてそれではなぜ始めに読んだときに、何かしっくりしない感じを
覚えたのだろうか。
読み直していて、はたと気が付いたことがある。
この短編集の第一話は『父の詫び状』である、出だしは伊豆から
もらった大きな伊勢海老が籠から抜け出して夜玄関の廊下を
這い回るところから始まる。
無論、伊勢海老が風流に廊下を徘徊するわけはなく、多分水を
求めて必死で這い回ったのであろう。
我が家も以前知り合いから大量の車えびをいただいたことがある。
一度にはとても食べきれないので、新聞紙を濡らして何層かに敷き
その間に何匹かの車えびを入れておいた。
そうすると長持ちすると聞いたからである。
ところがこの車えび夜中にギイギイ鳴くのである。
まるで『羊たちの沈黙』のように。(ちょっと大げさか)
そんなことがあり、それが私のトラウマになっていて伊勢海老が
描写された情景を無意識に排除していたかもしれない。
そんなわけでこのエッセイは私の読んだ中でも、屈指の名作であること
がわかった。
この短編集の中の『兎と亀』中でアマゾンのジャングルの上を
飛行機で飛ぶ話があり、その中で飛行機の墜落の話が出てくる。
向田邦子さんは1981年に台湾で飛行機事故により急逝されているので
それを思い出しながら読んだ、齢51は惜しいことをした。
2009年05月29日 Posted by igoten at 07:13 │Comments(0) │読書
国語入試問題必勝法
 国語入試問題必勝法
国語入試問題必勝法 清水 義範 (著)
「BOOK」データベースより
ピントが外れている文章こそ正解!問題を読まないでも答はわかる。国語が苦手な受験生に家庭教師が伝授する解答術は意表を突く秘技。国語教育と受験技術に対する鋭い諷刺を優しい心で包み、知的な爆笑を引き起こすアイデアにあふれたとてつもない小説集。吉川英治文学新人賞受賞作。
ピントが外れている文章こそ正解!問題を読まないでも答はわかる。国語が苦手な受験生に家庭教師が伝授する解答術は意表を突く秘技。国語教育と受験技術に対する鋭い諷刺を優しい心で包み、知的な爆笑を引き起こすアイデアにあふれたとてつもない小説集。吉川英治文学新人賞受賞作。
本屋さんにこの本が並んでいると単なる大学入試の為の参考書と 間違えるだろうが、これはパロディである。
間違って買ってしまった受験生には心からお悔やみ申し上げる。
たぶんこの本を読んでおかしさの為転げ回ったぶん、受験勉強が遅れたに違いない。
あの丸谷才一にして「知的な爆笑を引き起こすアイデアにあふれた とてつもない小説」言わさしめた鬼才清水 義範の小説。
読んでいるうちにどこまでは本当でどこまでがパロディか全く わからなくなる。
だいたい高校入試の国語の問題や、大学入試の国語の問題は 時々出題者の頭の中を覗きたくなる衝動に駆られる。
フロイトの「精神分析学」を徹底的に茶化した「猿蟹合戦とは何か」も良い。
知的な笑いに飢えている人には持って来いの短編集である。
2009年05月28日 Posted by igoten at 07:09 │Comments(8) │読書
かもめ食堂
 かもめ食堂
かもめ食堂 群 ようこ (著)
「BOOK」データベースより
ヘルシンキの街角にある「かもめ食堂」。 日本人女性のサチエが店主をつとめるその食堂の看板メニューは「おにぎり」。 けれど、お客といえば、日本おたくの青年トンミただひとり。 映画「かもめ食堂」の原作。
ヘルシンキの街角にある「かもめ食堂」。 日本人女性のサチエが店主をつとめるその食堂の看板メニューは「おにぎり」。 けれど、お客といえば、日本おたくの青年トンミただひとり。 映画「かもめ食堂」の原作。
日本人の普通の女の子がフィンランドのヘルシンキで食堂を始める。
そこにやってきた妙に訳ありの2人の日本人女性が店を手伝うことになる。
ねぜヘルシンキなのというようなことは書かれていない。
なんとなく透明感のあるヘルシンキの街がこの小説の舞台には
ぴったりの感がある。
本も読みDVDも観ると、後になっていったいこの印象はどっちのものだったか、
区別が難しくなる。
つまり映画の方も原作の雰囲気を大切にして良くできているといえるのだ。
それにしてもこの表紙のへたくそなカモメの絵は何だ。
まあそれはそれとして、群ようこ の文章はテンポが良くて深刻にならない。
色々などたばた劇があるのだが、簡単に解決してしまう。
だから、すたすた、さらさら読んでしまって、しかも何か心が温まるものが残る。
フィンランド人のくそまじめで融通が利かないところも良く出ている気がした。
私がフィンランドで会ったあの大男はストロールマンといったが、
今は何をしているのだろうか、牛乳をまるで敵のように飲んでいた。
それとフィンランドのデパートで買ったガラスの花瓶、ちょっと高価だったので、
割れないようにシャツやパンツに包んで持ってきたが、この前気が付いたら
下の所が少し欠けていた、きっと女房がどこかにぶつけたに違いない。
さてこの本の何か特徴的な一節を紹介しようと思ったのだが本そのものが何処かに
行ってしまって見つからないのでご容赦願いたい。
実は「ぢぞうはみんな知っている」も何処かに......
ところでこのブログの「ぢぞうはみんな知っている」の最後に
「この作者相当物事にこだわらなく、度胸が良いと思われる」と
書いたがこの理由を申し上げる。
映画のほうには無いのだが、お金の無い主人公のサチエがいかにして
フィンランドで食堂を開くことが出来たのかは、なんと宝くじに当たったことに
なっている、宝くじに。
普通の作者だったら絶対こんな設定にはしない、父と別れた母が大富豪と結婚して
遺産が入ったとか、まあ何かひいひい言いながら凝った設定を考えるでしょうが、
群ようこはそんな面倒なことはしない、
「弱ったな、まあいいか宝くじにでも当たったことにしておけ」とまあこんなのり
なのだろう。
なぜそのような性格なのかのヒントは上の「著者」の中に書かれている。
度胸がよくて、物事にこだわらない、それでいて書いたものが映画にもなるのだ。
群ようこ 恐るべし!
2009年05月27日 Posted by igoten at 07:23 │Comments(0) │読書
剣法奥儀

ここに一人の天才剣豪作家がいる。
五味康祐である。
彼は昭和28年「喪神」で芥川賞を受賞している。
いくら昔でも、いったい剣豪小説で芥川賞が取れるものなのか。
次の文を読んでいただきたい。
これは心極流「鷹之羽」の一節である。
二人の剣豪が城主光政の前で川に浮かんでいる
桃を切って腕比べをする段である。
剣豪の一人は永庵、誰もが達人と認める剣の使い手である。
対するは佐太夫、佐太夫は以前、兵法指南でありながら
他流試合に負けて城下を去った。
そして2年後、再び城下に現れた佐太夫の変わりはてた姿...
いったいどのような修業を積んだのか、皆が息を詰めて見守る。
先ず永庵が片袖を抜いて、太刀の鞘を払った。
それから川上に控える役人へ、「お流しあれ」と声をかけた。
役人は桃を一つ、流れに浮かべる。
流れはさして早くない。
浮きつ、沈みつ....次第に永庵の前に近寄って来る。
永庵は右八双に構えて、桃を待った。
桃は流れ寄った。
岸から一歩水中に踏み込むや永庵はサット一太刀斬った。
目にもとまらぬ閃光が桃をかすめたと、一同には見えただけである。
一旦沈んで、浮き上がった桃は赤い核を開いている。
居並ぶ一同の口から同時に嘆声が洩れた。
.....
次に佐太夫が岸に進み出た。
佐太夫は永庵の対岸でさきほどから見ていたのである。
「お流しくだされ。」
と呼びかけた。役人は次の桃を流した。
狂気と見えた程の修行の術を今こそ見る事が出来る。
光政以下、一様にそう思って見守る。
桃は流れ寄ってくる。......
佐太夫は太刀を水平に構え、川面へ橋を架けるが如くそれを渡した。
白刃と水面にはほぼ一尺余の空間があった。
折から夏の陽を受けて水面に刀身の影が落ちている
桃は音もなくその影の下を流れたが、それだけである。
佐太夫は呆けたように水平に太刀を構えて立ち、桃は流れすぎた。
あきれ果てて、一同は流れ去る桃を見、佐太夫の顔を窺い、
且、桃を見送った。
桃は、流れて行って、フト岸に当たったとき真っ二つに割れて、
流れた。
どうであろうか、芥川賞を取るにはそれだけの理由があるのだ。
2009年05月26日 Posted by igoten at 07:45 │Comments(0) │読書
美味放浪記
 美味放浪記
美味放浪記 檀 一雄 (著)
「BOOK」データベースより
およそ咀嚼できるものならば何でも食ってしまうというのが人類の大きな特質であるが、 わけても著者はその最たるもの。先入観も偏見も持たず、国内国外を問わず、 著者は美味を求めて放浪し、その土地土地に根付く人々の知恵と努力を食べる。 現代に生きる私たちの食生活がいかにひ弱でマンネリ化しているかを痛感させずにはおかぬ、豪毅なエッセイ集。
およそ咀嚼できるものならば何でも食ってしまうというのが人類の大きな特質であるが、 わけても著者はその最たるもの。先入観も偏見も持たず、国内国外を問わず、 著者は美味を求めて放浪し、その土地土地に根付く人々の知恵と努力を食べる。 現代に生きる私たちの食生活がいかにひ弱でマンネリ化しているかを痛感させずにはおかぬ、豪毅なエッセイ集。
檀 一雄は私生活も豪快であったが、この本の内容も豪快である。
国内編の食べ歩きも面白いが、外国での食べ歩き記は特に面白い。
この本の外国編の最初にスペインの有名な豚肉のハム『ハモンセラーノ』の
事が出てくる。
私も以前先輩からスペインに行ったらこのハモンセラーノとうなぎのしらす
のオリーブオイル煮を食べておけと言われたことがある。
その後、スペインのバルセロナに行った時にそのことを思い出して、
レストランでうなぎのしらす煮を頼んだが季節料理なので今はないと断られた、
世界的なうなぎの幼魚不足の昨今では季節でも食べられなくなっているのだろ、
惜しいことをした。
ただしハモンセラーノは滞在中は毎日食べていたような思い出がある。
同じ生ハムにイタリアのパルマハムというのがある。
パルマというのはあのサッカーのチームで有名なパルマ地方のことである。
ここでパルマハム・ウィズ・メロンというのを食べたことがある、初めは
「え!メロンとハムですか」とその組み合わせの奇異さに思わず腰が引けたが、
食べて見るとその美味しさにまさに舌を巻いた。
切ったメロンに薄いパルマハムが網のようにかけてあり、
甘いメロンに少ししょっぱいハムの味がアクセントとなり、
えもいわれぬ食感をかもし出す。
日本でもスーパーなどに薄くきった生ハムが売っているのであれを
メロンにかければ良いのである。
今度家でやってみようと思うのだが、メロンがある時はハムがなく
ハムがある時はメロンが無い、一期一会、出会いは難しい。
2009年05月25日 Posted by igoten at 07:30 │Comments(0) │読書
ただの歌詞じゃねえかこんなもん
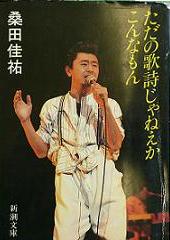 ただの歌詩じゃねえか、こんなもん
ただの歌詩じゃねえか、こんなもん桑田 佳祐(著)
「BOOK」データベースより
シンガー=ソング・プロレスラーを自認するニューミュージック界 の天才児が、腕によりをかけて料理した魔法のコトバたち。
シンガー=ソング・プロレスラーを自認するニューミュージック界 の天才児が、腕によりをかけて料理した魔法のコトバたち。
あの『TUNAMI』という歌の歌詞が典型的に
そうなんだが、サザンの歌は言葉遊びの歌詞が多い。
ふぅっと意味がわからなくなりそうになってまた元に
引きもどされるような微妙な言葉の遊びが軽いようで
妙にこころに残る祭りの夜、こころ洗うせせらぎの
いとしき人の胸の中なのだ。
で、
『いとしのエリー』の型破りな歌詞の裏側がわかるかも、
という期待でこの本を購入。
『いとしのエリー』の説明は
...そんな中で、いよいよ芸能人として二枚目のシングルだから、
どうしたって『勝手にシンドバット』の線をねらって作らざるを
得ない。
無論やりりたくなかったけどね。
だから、『気分しだいで責めないで』がヒットした次、
三枚目のシングル『いとしのエリー』の時には、
もう開きなおちゃった。
よし、ビートルズを思い出そう、ってことになった。
彼らが映画『Let It Be』の中で一生懸命セッションしている、
ああいう音楽が出来たらいいね、ってね。
ひゃー!これなんだ、「一生懸命セッションしている」ってどういう意味だ、
業界用語か?
誰か教えて!
【ウィキペディア】
セッション:
複数のミュージシャンが共に演奏すること。
一度きりのものなど、継続的でないものを指すことが多い。
2009年05月24日 Posted by igoten at 08:05 │Comments(2) │読書
賢者の贈り物
 賢者の贈り物
賢者の贈り物オー・ヘンリー(著)
「BOOK」データベースより
貧しい夫妻が相手にクリスマスプレゼントを買うお金を工面しようとする。 妻のデラは、夫のジムが祖父と父から受け継いで大切にしている金の 懐中時計を吊るす鎖を買うために、 自慢の髪を美容室でバッサリ切り落とし、売ってしまう。 一方、夫のジムはデラが欲しがっていた鼈甲の櫛を買うために、 自慢の懐中時計を質に入れていた。
貧しい夫妻が相手にクリスマスプレゼントを買うお金を工面しようとする。 妻のデラは、夫のジムが祖父と父から受け継いで大切にしている金の 懐中時計を吊るす鎖を買うために、 自慢の髪を美容室でバッサリ切り落とし、売ってしまう。 一方、夫のジムはデラが欲しがっていた鼈甲の櫛を買うために、 自慢の懐中時計を質に入れていた。
短編小説の名手オー・ヘンリの短編小説のお手本ともいうべき作品である。
短い一編の小説の中に短編小説で必要なすべての要素が詰まっている。
筋書きは上にも書いてあるが、
貧乏な若い夫婦がお互いのクリスマスプレゼントを買おうとしている。
夫は妻の為に妻の美しい髪に飾る鼈甲の櫛を、妻は夫の為に夫が持つ
自慢の懐中時計にあう鎖をプレゼントに決めている。
しかし貧乏な二人にはそれらを買うお金がない。
そこで妻は自分の髪を売って懐中時計の鎖を買い、夫は妻の為に
自慢の懐中時計を売って櫛を買うのである。
この短編次の文で始まる。
1ドル87セント。
それで全部。
しかもそのうち60セントは小銭でした。
小銭は一回の買い物につき一枚か二枚づつ浮かせたものです。
乾物屋や八百屋や肉屋に無理矢理まけさせたので、しまいに、
こんなに値切るなんてという無言の非難で頬が赤くなるほどでした。
デラは三回数えてみました。
でもやっぱり1ドル87セント。
明日はクリスマスだというのに。
(結城浩 訳)
どうであろうか
「彼女の手の中にあるのは1ドル87セント、そしてそれがすべてであった。」
などと言うつまらない書き出しはしない、さすがに短編小説の名手である。
この短編小説は下のHPで閲覧出来る。
賢者の贈り物
5分で読めるので、読んだことのない人は是非読んでみてほしい。
しばらくの間幸せになれること請け合いである。
2009年05月23日 Posted by igoten at 07:01 │Comments(2) │読書
世界一周ビンボー大旅行
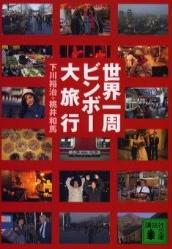 世界一周ビンボー大旅行
世界一周ビンボー大旅行 下川裕治(著)
「BOOK」データベースより
旅本世界のトンデモ本 『12万円で世界を歩く』の名コンビ復活! 目的はニッポン! 大阪南港を旅立ち上海、ウランバートル、酷寒のシベリアをひた走る。列車とバス、 船を乗り継ぎ地球を西へ、西へ。地を這うような旅の記録。 目的地は?それはニッポン!!大阪を旅立ってひたすら西へ、西へ。 上海、北京、ウランバートルを経て酷寒のシベリアをひた走り、 ベルリン、アメリカヘ。列車とバス、船を乗り継ぎ地を這うような旅は続いた。 旅本世界の金字塔『12万円で世界を歩く』の名コンビが、再び激動の地球を回る。
旅本世界のトンデモ本 『12万円で世界を歩く』の名コンビ復活! 目的はニッポン! 大阪南港を旅立ち上海、ウランバートル、酷寒のシベリアをひた走る。列車とバス、 船を乗り継ぎ地球を西へ、西へ。地を這うような旅の記録。 目的地は?それはニッポン!!大阪を旅立ってひたすら西へ、西へ。 上海、北京、ウランバートルを経て酷寒のシベリアをひた走り、 ベルリン、アメリカヘ。列車とバス、船を乗り継ぎ地を這うような旅は続いた。 旅本世界の金字塔『12万円で世界を歩く』の名コンビが、再び激動の地球を回る。
今回はバックパッカーの超カリスマ、何と松本市出身の下川祐治
の登場である。
下川祐治といえば、アジアの貧乏旅行に関しては彼の右に出るものはいない。
貧乏旅行に関する著作数数知れず、独特の下川節につられてふらりとアジアの旅
に出てしまった若者数知れず。
私も彼の大ファンで彼が書いた本はほとんど読んだ。
大したお金も持たずはっきりした目的も持たず、ふらりと旅に出る彼の姿は、
押しつけの目標と目の色を変えてお金を求めざるをえない我々の小市民的な
生活の対岸にある。(ん。。)
彼の書く本には、この手の本によくある退廃的な雰囲気はなく、
ユーモアを交えた暖かな表現で、行く先々の人々を大まかにしかも的確に描写する。
彼の本を読んでいると、ふと、ほんとうは最も難しい種類の旅なので
あるが、自分もこんな旅に簡単に出かけられるという錯覚に陥る。
さてこの『世界一周ビンボー大旅行 』は船と列車を乗り継ぎ、日本から
イギリスまで行ってしまうというものである。
(最後はイギリスから航空機でアメリカまで行くのであるがこれはおまけ)
特に北京からモスクワまでの列車の旅がクライマックスで、列車の中の様子や
列車が到着する駅の人々の様子が丹念に描かれている。
この本の中に次のくだりがある。
シベリアの駅に降り立った筆者らが物売りの女性たちを見て感じたことである
僕は彼らの視線が気になっていた。ホームに降りた僕らを見つめる瞳が 一様に暗いのである。彼らは無言ではあるが。だが、その視線は、 「買ってほしい」とまとわりついてくる。まるで蛇の目のように、暗く 湿っているのだ。シベリアに入ったとき、同じ車両にいうイングランド 人女性がこんなことを言った。
「ロシアに入って変わったこと。そうね、女性がみな、化粧をしている ことかな。それにいいものを着ている。だって中国はひどいじゃない。 大都会の若者はおしゃりになってきたけれど、市場のおあばちゃんなんて、 誰一人化粧をしていないし、着ているものだって、粗末なものよ。」
確かにロシアン人は食べるものは粗末でも、ちゃんとした物を着ている、
中国人は着る物など無頓着で旨いものを食べるのである。
ロシア当時確かには貧しかった。
こんな笑い話がある。
『あるロシア人が日本に来て、ショーウインドウ一杯に並べてある 商品を見て驚いて言った「日本人というのはよほど貧乏に違いない、 ロシアならあれだけの物を並べておけば、1時間で売り切れてしまう。』
さて通常下川祐治の本には彼自身のイラストが所々に入れられていることが多く、
これがまた彼の本のひとつの味になっているのだけれど、この本は専門のカメラマンが
同行して、その時々の情景を白黒の写真で撮影している。
そしてこの白黒の写真がまた素晴らしい、特に人物の表情が。
それもそのはずこのカメラマンは桃井和馬と言って押しも押されぬ一流の
フォト・ジャーナリストなのである。
そうこの本は1冊で2度美味しいのである。
それにしても白黒の写真はいいなぁ!
最近はカラー写真ばっかりだが、白黒写真は単純な2色の明暗の中に
無限の色が見えるようで。
たぶんフィルムはトライX、カメラはキャノンだろう。
(ニコンだったらもっと良いのに)
この本はパラパラと写真だけ見てもよし、所々の文章を拾い読みしてもよし
旅好きにはもってこいの一冊なのだ。
2009年05月22日 Posted by igoten at 07:27 │Comments(4) │読書
癒す心、治る力
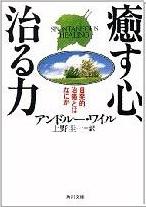 癒す心、治る力
癒す心、治る力アンドルー ワイル (著)
「BOOK」データベースより
人には自ら治る力がそなわっている。その治癒力を活性化させることで、 絶望的な病から奇跡的に生還した人は少なくない。現代医学から、自然生薬、 シャーマニズムまで、人が治るメカニズムを究めたワイル博士が、 自らの臨床体験をもとに、実際の治癒例と処方を具体的にわかりやすく記し世界的ベストセラーとなった医学の革命書。
人には自ら治る力がそなわっている。その治癒力を活性化させることで、 絶望的な病から奇跡的に生還した人は少なくない。現代医学から、自然生薬、 シャーマニズムまで、人が治るメカニズムを究めたワイル博士が、 自らの臨床体験をもとに、実際の治癒例と処方を具体的にわかりやすく記し世界的ベストセラーとなった医学の革命書。
健康フリークでこの本と著者を知らない人はいないであろう。
ワイル博士の講演には何万もの人が集まり、彼の姿を見ただけで
病気が癒えてしまう人が居るというほどのカリスマ的存在である。
しかも彼は薬用植物の世界的権威なのである。
彼の考え方の根本は『ひとには自然の治癒力が備わっている』ということである。
ではなぜ病気にかかるかとう疑問に対して次のように応えている。
『治癒系はつねに存在し、いつも作動しているが。
心身のバランスが失われると、治癒系は必ずバランスを回復するための
準備にかかる。しかし、ときにその回復能力が、必要とされる仕事量に
追いつかないことがある。』
重要なのは身心のバランスである。
そして彼は5つの重要項目をあげる。
●からだは健康になりたがっている。
●治癒は自然の力である。
●からだはひとつの全体であり、すべての部分はひとつにつながっている。
●こころとからだは分離できない。
●治療家の信念が患者の治癒力に大きく影響する。
治癒力を高めることが健康を維持しまた病気から脱出する最も効果的な
方法であると彼は説く。
そしてこれは『悪いところは切り取ってしまえ』という西洋医学とは
一線を画す考え方なのである。
彼は治癒力を高める食べ物として、にんにく、ブロッコリー、オリーブオイル
をあげ、次のような料理法まで紹介している。
『大型のブロッコリー一房を用意し、太い茎の固い下部だけを切り落とす。 太い茎の残りは繊維層の下まで皮をむき、ざくざくとたべやすい大きさに切る。 ブロッコリーの頭の部分も食べやすい大きさに切り、固い茎は軽く皮をむいておく。 水洗いしてから、1/4カップの水を入れた鍋にいれ、一番搾りのオリーブ油大さじ 一杯、塩少々、刻みニンニク4,5片を加える。蓋をして煮立たせ、ブロッコリー の緑色が鮮やかさをまして、固めの歯ざわりになったところで蓋をとる。 5分はかからない。そのまま残り湯を蒸発させ、すぐに食卓に出す。』
これはイタリア人がよく作る、ズッキーニの料理方法だな。
重要なのはにんにくをたくさん使うところと『一番搾りのオリーブ油』すなわち
『エクストラバージンオイル』を使うところである。
このくらいなら私にも出来そうであるが、まずはブロッコリーとカリフラワーの
違いから調べなくては・・・
このほか小麦のふすまも植物繊維で体に良いと書いてあったので、
近くのスーパーでふすま入りのシリアルを買ってきて、朝食としてミルクを
かけて食べてみたが、まずくて3日と続かなかった。
よく考えてみたら私は冷たい牛乳が苦手なのだ、かといって暖かい牛乳をシリアルに
かけると、シリアルがぐなぐにゃになってなんだか猫のゲロのような・・・
健康になるためには忍耐と努力が重要なのだ。
私は呼吸法が健康維持に重要な役割を持っていると考えており、いろいろと
本などを読んで調べているのだが、これに関しては次の記述がある。
『就寝前や起床時に実行したい呼吸法なので、このトレーニングは仰向けに 寝ながら行うといい。目を閉じて、両腕はからだの脇に。呼吸を変えようと せずにただ呼吸に集中する。そして、息を吸うたびに「宇宙がわたしのなかに息を 吹き込んでいる」とイメージし、 息を吐くたびに「宇宙が私から息を吸い込んでいる」とイメージする。 自分を「宇宙に呼吸される者」として受け身にイメージするのだ。 宇宙が息を吹き込むたび、その息がからだ全体に、指やつま先にまで浸透していくのを 感じ、味わう。その意識状態のままで10回、吸気と吸気をくり返す。』
なるほどこれは自律神経の訓練にはよさそうである。
ただしこのトレーニングが終わった後、腕を曲げて握りこぶしを強く握って、
「エイ!」と腕を伸ばしながら手を広げてて覚醒する動作を2~3回位やった方が
よさそうである。
そのほかにこの本は盛りだくさんで、健康に自信のない方は、ぜひ座右に
一冊ほしい本である。
この本を置いておくだけで何か健康になれそうな・・・、それはないか。






