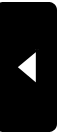家族八景
 家族八景
家族八景筒井康孝 (著)
「BOOK」データベースより
筒井康隆のSF小説。1970年から1971年にかけて『小説新潮』『別冊小説新潮』 に掲載された8編の短篇からなる。第67回直木賞候補作。 後に出版された『七瀬ふたたび』『エディプスの恋人』をあわせた 「七瀬シリーズ」「七瀬三部作」のひとつ。
筒井康隆のSF小説。1970年から1971年にかけて『小説新潮』『別冊小説新潮』 に掲載された8編の短篇からなる。第67回直木賞候補作。 後に出版された『七瀬ふたたび』『エディプスの恋人』をあわせた 「七瀬シリーズ」「七瀬三部作」のひとつ。
先日NHKで『七瀬ふたたび 』を放送していた。
これを観ていて「ちょっと待て、こんなストーリーだったかな?」と
引っ張り出して読みなおしたのがこの本。
NHK放送の『七瀬ふたたび 』と同じ主人公で心が読める七瀬が登場する。
しかしこの本は『七瀬ふたたび 』とは別物と考えてよい。
この本をNHKが原作に忠実にドラマ化することは絶対に出来ない。
なぜならばこの本にはいたるところに性の描写があるからだ。
人の心を読むということはある意味で精神分析学に似ている、この小説
が書かれた当時は精神科医のジークムント・フロイトの『夢判断』などが
流行った時代で、フロイトは夢を『抑圧された性衝動の代償行動』と定義づけた
のである。
この小説の中にも代償行動なる言葉が出てくるので、たぶん作者はフロイトの
影響を受けているのだろう。
さて主人公は人の心の中を見ることが出来る18歳のお手伝いさんの少女七瀬、
彼女がいく先々の家でそこの住人の心を覗き憎悪、嫉妬、親子の兄弟の
確執を見る。
この小説にはヒロインは登場しない、主人公の七瀬は人の心を読むが
その人が窮地に陥っても助けたりはしないのである。
彼女がその人たちにいだく感情は嫌悪と憎悪がほとんどであり、
たとえば生きている人間が棺桶の中に入れられて焼き殺されようと
していても彼女は助けないのである。
すなわち、ここに登場する七瀬は、『他人の意識を覗いて見たい』
と誰しもが持つ願望を実行する代理人なのであって、
他人を助けるためにその人の心を覗いてみたいという人が少ないように、
七瀬もまた助けるために人の心を覗くのではない。
この小説はSFであるがホラーでありミステリーである。
この本に一切救いは無いが唯一つあるとするなら、
『やはり他人の心も自分と同じように汚かったか』または
『私に心はそれほど汚くない』と読者に半ば安心させることであり、
そう思った瞬間に、読者は鬼才筒井康孝の術中に見事陥ったことに
なるのである。
本の背表紙にこんな解説が載っている。
人間心理の深層に容赦なく光を当て、平凡な日常生活を営む小市民
の猥雑な心の裏面を、コミカルな筆致で、ペーソスにまで昇華させた、
恐ろしくも哀しい本である。
だらだらした推理小説に飽き方にお勧めの小説であり、短編集なので
手軽に読めるが不眠症ぎみの人は寝る前に読まない方が良い。
2009年05月20日 Posted by igoten at 07:35 │Comments(7) │読書
漂流
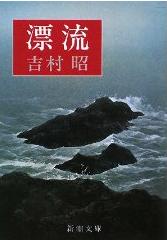 漂流
漂流吉村 昭 (著)
「BOOK」データベースより
江戸・天明年間、シケに遭って黒潮に乗ってしまった男たちは、 不気味な沈黙をたもつ絶海の火山島に漂着した。水も湧かず、 生活の手段とてない無人の島で、仲間の男たちは次次と倒れて行ったが、 土佐の船乗り長平はただひとり生き残って、12年に及ぶ苦闘の末、ついに生還する。 その生存の秘密と、壮絶な生きざまを巨細に描いて圧倒的感動を呼ぶ、長編ドキュメンタリー小説。
江戸・天明年間、シケに遭って黒潮に乗ってしまった男たちは、 不気味な沈黙をたもつ絶海の火山島に漂着した。水も湧かず、 生活の手段とてない無人の島で、仲間の男たちは次次と倒れて行ったが、 土佐の船乗り長平はただひとり生き残って、12年に及ぶ苦闘の末、ついに生還する。 その生存の秘密と、壮絶な生きざまを巨細に描いて圧倒的感動を呼ぶ、長編ドキュメンタリー小説。
人は何が怖いかといって、孤立することほど怖いことはない。
無人島に一人だけとり残されるというのは、いわば究極の孤独である。
江戸時代、漁船の遭難によって漂流、そしてかれらが漂着した島は
水も草木もない現在の鳥島。
ただアホウドリの大群だけが彼らを待つ、この鳥を取って食べる以外に
生きる方法はない。
偏食で死んでゆく仲間、唯一の食料の、渡り鳥のアホウドリが飛び去って
行ってしまう恐怖。
何人かいた仲間も次々に死んでしまい、ついに一人に....
これは強靭な精神力と知恵で絶望的な状況を生き延びてゆく感動の
ドキュメンタリー小説である。
次の一節は他の遭難者が島に来たくだりである。
..
「井戸は有るのでしょうね?」
八五郎が、気づかわしげにたずねた。
..
「井戸などあるものですか」
長平が、さりげなく言った。
「ない?」
「そうです。この島には、小川ないし、泉もない。
雨水をためて飲む以外にはないのです」
..
「それに......」
と、長平は言った。かれの顔に、悲しげな表情がうかんだ。
「食べ物も、鳥を殺生して生きていく以外にない。
穀物なども、食べられる野草もない。貝をひろったり、たまにかかる
魚を釣るくらいのもので....」
長平は、うつろな眼をして言った。
絶望的な状況でも最後まであきらめない者だけが生き残れるのである。
2009年05月19日 Posted by igoten at 07:39 │Comments(0) │読書
ああ、恥ずかし
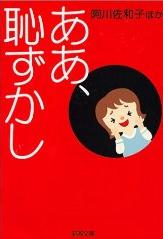 ああ、恥ずかし
ああ、恥ずかし阿川 佐和子(著)
「BOOK」データベースより
白いワンピースで雨に降られて下着バッチリ。泥酔状態で乗せられたパトカーの中で大はしゃぎ。下書きのまま、うっかり押したパソコンの送信ボタン。服の裾から出てきた、昨日脱いだはずのストッキング。思い出すたびに赤面、できれば記憶を消去したい、そんな“恥ずかし体験”を、作家・イラストレーター・女優・タレントなど女性ばかり70人が思い切って明かした大爆笑のオリジナル文庫。
白いワンピースで雨に降られて下着バッチリ。泥酔状態で乗せられたパトカーの中で大はしゃぎ。下書きのまま、うっかり押したパソコンの送信ボタン。服の裾から出てきた、昨日脱いだはずのストッキング。思い出すたびに赤面、できれば記憶を消去したい、そんな“恥ずかし体験”を、作家・イラストレーター・女優・タレントなど女性ばかり70人が思い切って明かした大爆笑のオリジナル文庫。
ホテルのスリッパを履たままチェックアウトしてしまったり、食事会の時ステーキを
テーブルの真ん中まで飛ばしてしまったり、私も恥ずかしいことには事欠かないが、
人の失敗談を聞くことほど楽しいことはない。
誰でも顔から火が出るほど恥ずかしい失敗の経験は有るだろう、そんなことが
トラウマになっていたら、この本を読むべし。
集めも集めたりなんと有名人70人の失敗談が書かれている。
中にはそんなことはちっとも恥ずかしい事じゃ無いじゃん、というものもあるが
よくぞ書いた、と勇気を褒め讃えたくなるのもある。
2009年05月18日 Posted by igoten at 07:25 │Comments(3) │読書
イワン・デニーソヴィチの一日
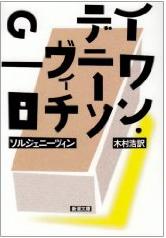
イワン・デニーソヴィチの一日
ソルジェニーツィン(著)
「BOOK」データベースより
午前五時,ラーゲリ(収容所)ではいつものように起床の鐘がなった.
また長い一日がはじまるのだ.
――身をもって体験したスターリン時代のラーゲリを舞台に作者は
異常な状況下で人々が露わにする多様な性格と行動を描き,
人間性の圧殺者を正視し告発する.
強靭なヒューマニズムの精神と高度の芸術的技量に裏うちされた作品.
午前五時,ラーゲリ(収容所)ではいつものように起床の鐘がなった.
また長い一日がはじまるのだ.
――身をもって体験したスターリン時代のラーゲリを舞台に作者は
異常な状況下で人々が露わにする多様な性格と行動を描き,
人間性の圧殺者を正視し告発する.
強靭なヒューマニズムの精神と高度の芸術的技量に裏うちされた作品.
第二次世界大戦後、ソ連人はヒットラーという虎が去った後に、
スターリンという狼が現れたことを知る。
この狼は陰湿で執拗であった、正式には200万人のソ連人が
弾圧により殺されたとされるが、一説には1000万人を超える
言われる。
これは強制収容所に入れられた経験をもとに、その絶望的な
状況を、時にユーモアを交え暖かいタッチで描いた小説である。
この物語は次の文で終わっている。
眠りにおちるとき、シューホフはすっかり満足していた。
一日の間に今日はたくさんいいことがあった。
営倉にはいれられなかったし、班は「社・主団地」へやられなかったし、
昼めしのときにカーシャを一杯せしめたし、
班長は作業パーセント計算をうまく〆たし、
シューホフは壁を楽しく積んだし、検査で鋸をみつけられなかったし、
夕方はツェーザリでひと儲けしたし、タバコを買ったし。
それから、病気にならずに直ってしまった。
一日が過ぎた。暗い影のちっともない、さいわいといっていい一日だった。
こんな日が、彼の刑期のはじめから終わりまで、三千六百五十三日あった。
うるう年のため、三日のおまけがついたのだ。......
まだベルリンに壁があったころ、その壁を抜けて西側から東に入った
事がある。
華やかな西ベルリンに比べて東側は何かじめじめして、暗く
まるで空気がよどんでいるような感じだったと記憶している。
あの壁が崩れるなどという事はその当時は想像だにしなかった。
『苛政(かせい)は虎よりも猛し』か。
私の好きなロシア民謡に次の歌がある。
悲しい歌嬉しい歌 たくさん聞いた中で
忘れられぬひとつの歌 それは仕事の歌
忘れられぬひとつの歌 それは仕事の歌
ヘイこの若者よ ヘイ前へ進め さぁみんな前へ進め
イギリス人は利口だから 水や火などを使う
ロシア人は歌をうたい 自ら慰める
ロシア人は歌をうたい 自ら慰める
ヘイこの若者よ ヘイ前へ進め さぁみんな前へ進め
死んだ親が後に残す 宝物は何ぞ
力強く男らしい それは仕事の歌
力強く男らしい それは仕事の歌
ヘイこの若者よ ヘイ前へ進め さぁみんな前へ進め
本来ロシア人は素朴で忍耐強い農耕民族である。
2009年05月17日 Posted by igoten at 07:50 │Comments(4) │読書
歌謡曲の時代
阿久 悠(著)
「BOOK」データベースより
「勝手にしやがれ」「あの鐘を鳴らすのはあなた」 「ペッパー警部」……。今も人々が口ずさむ、五千を超すヒット曲を作詞し、 平成十九年に世を去った阿久悠。「歌謡曲は時代を食って巨大化する妖怪である」 と語った稀代の作詞家が、歌手との思い出、創作秘話、移り行く時代を、鋭く、 そして暖かな眼差しで描く。歌謡曲に想いを託し、 日本人へのメッセージを綴った珠玉のエッセー。
「勝手にしやがれ」「あの鐘を鳴らすのはあなた」 「ペッパー警部」……。今も人々が口ずさむ、五千を超すヒット曲を作詞し、 平成十九年に世を去った阿久悠。「歌謡曲は時代を食って巨大化する妖怪である」 と語った稀代の作詞家が、歌手との思い出、創作秘話、移り行く時代を、鋭く、 そして暖かな眼差しで描く。歌謡曲に想いを託し、 日本人へのメッセージを綴った珠玉のエッセー。
なんと阿久 悠 は5000もの作詞をしたのである。
そんな阿久 悠がほんのちょっと作詞家の裏側を見せてくれる。
つまり、通常の人間では到底達成できないマジックの種を
ちょっとだけ教えてくれるのがこの本である。
さて5000もの詞があるので、どれが彼の代表作なのか議論が分かれるところ
であるが、私は彼の代表作は「あの鐘を鳴らすのはあなた」思っている。
あなたに逢えてよかった
あなたには 希望の匂いがする
つまずいて 傷ついて 泣き叫んでも
さわやかな 希望の匂いがする
町は今 眠りの中
あの鐘を 鳴らすのは あなた
人はみな 悩みの中
あの鐘を 鳴らすのは あなた
これは愛や恋の歌ではない、あなたに逢えてよかったのは、
あなたの姿や、声が好きなのではなく、「希望の匂いがする」からである。
そしてあなたからは「さわやかな希望の匂いがする」のである。
あなたは私を愛してくれたり、幸せにするのではなく、
「あの鐘を鳴らす」のである。
あの鐘って何だ!
阿久 悠は次のように書いている
そもそも、「あなた」とはいったい誰のことだったのだろうか。
そんな時代の中での遭遇を希望と感じられるあなたが、ただの
恋人やボーイフレンドであるわけがない。
ましてや、和田アキ子がより大きく見えるようにと歌った歌なのだから...。
面白かったり、心やさしかったり、親切であったり、また、長い髪で、
細いジーパンが似合って、ギターを小器用にかき鳴らして、
自由そうに見えて、何にも拘束されたくなくすぐに旅に出る--
そういう好ましい若者の姿と、この「あなた」は明らかに違う。
うーん、しばらくはこれを超える歌は出てこない予感が。
個人的には

誰かがワルツを踊っています
幸せあふれた二人です
私は飲めないお酒を飲んで
泣きたい気持ちをおさえます
海鳴り漁火海辺のホテル
一人に悲しいワルツの調べ
が好きかな。
2009年05月16日 Posted by igoten at 07:29 │Comments(2) │読書
笑の大学
笑の大学
三谷幸喜(脚本)
役所広司(出演者)
稲垣吾郎(出演者)
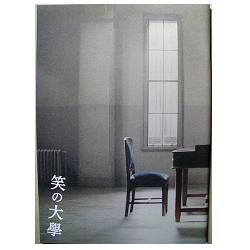
日本でもこんな上質な笑いの映画が出来るのかと感心するほど面白い。
建物や室内は結構凝ったものであるが、出演者は殆ど二人だけの映画である。
それもそのはず、これは舞台用の脚本を映画用に直したものなのだ。
稲垣五郎扮する真面目くさった喜劇作家の椿のニコリともしない演技がいい。
生まれてこの方笑ったことが無いという役所広司扮する検閲官との絡み、
話が進むにつれて、いったいどっちが喜劇作家でどっちが検閲官か
わからなくなる心憎いストーリー。
見ている方は三谷幸喜マジックに完全にはまってしまう。
最後に『金色夜叉』の名古屋版が出てきて、
「おみゃーさんは、お宮さんではにゃーかい。」
ここで爆笑となる。
最後は少し悲しい結末が....
こんな面白い映画でも興行収入はたった7.2億円、日本人には
上品なユーモアは難しいのか。
三谷幸喜(脚本)
役所広司(出演者)
稲垣吾郎(出演者)
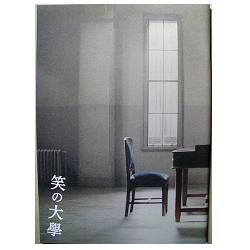
「BOOK」データベースより
昭和15年。日本に戦争の影が近づき、大衆娯楽の演劇にも検閲のメスが入っていた。 劇作家の椿一は、新しい台本の検閲のため、警視庁の取調室に出向く。 そこに待っていたのは、これまで心から笑ったことのない検閲官、向坂だった 。椿の新作を上演禁止にするため、向坂はありとあらゆる注文をつけるが 、椿は苦しみながらも、向坂の要求を逆手に取ってさらに笑える台本を作り上げていく。 こうして、2人の台本直しは、いつの間にか傑作の喜劇を生み出していくのだが…。
昭和15年。日本に戦争の影が近づき、大衆娯楽の演劇にも検閲のメスが入っていた。 劇作家の椿一は、新しい台本の検閲のため、警視庁の取調室に出向く。 そこに待っていたのは、これまで心から笑ったことのない検閲官、向坂だった 。椿の新作を上演禁止にするため、向坂はありとあらゆる注文をつけるが 、椿は苦しみながらも、向坂の要求を逆手に取ってさらに笑える台本を作り上げていく。 こうして、2人の台本直しは、いつの間にか傑作の喜劇を生み出していくのだが…。
日本でもこんな上質な笑いの映画が出来るのかと感心するほど面白い。
建物や室内は結構凝ったものであるが、出演者は殆ど二人だけの映画である。
それもそのはず、これは舞台用の脚本を映画用に直したものなのだ。
稲垣五郎扮する真面目くさった喜劇作家の椿のニコリともしない演技がいい。
生まれてこの方笑ったことが無いという役所広司扮する検閲官との絡み、
話が進むにつれて、いったいどっちが喜劇作家でどっちが検閲官か
わからなくなる心憎いストーリー。
見ている方は三谷幸喜マジックに完全にはまってしまう。
最後に『金色夜叉』の名古屋版が出てきて、
「おみゃーさんは、お宮さんではにゃーかい。」
ここで爆笑となる。
最後は少し悲しい結末が....
こんな面白い映画でも興行収入はたった7.2億円、日本人には
上品なユーモアは難しいのか。
2009年05月15日 Posted by igoten at 07:48 │Comments(4) │映画
挫折
 オバマ演説集
オバマ演説集バラク オバマ
「BOOK」データベースより
伝説の「基調演説」から「勝利演説」まで。「英‐日」完全対訳と詳しい語注付き。 CDには臨場感あふれる生の音声を収録。
伝説の「基調演説」から「勝利演説」まで。「英‐日」完全対訳と詳しい語注付き。 CDには臨場感あふれる生の音声を収録。

|
「英語の勉強とオバマ大統領の理解が同時に出来ると思い購入しました。」 「それと、CDが付いて1000円と安かったので.........」 |

|
「それで勉強になったの?」 |

|
「いい年をして物事はそんなに簡単では無い、 と言う事を再認識しました。」 「オバマ大統領の母は彼が5歳の時にインドネシア人と再婚して彼も ジャカルタに移りました。 そして10歳の時一人でハワイに住む祖父母の処へ一人で行きました。 彼の思想の裏にこのような生い立ちが関係するんでしょうね。」 |

|
「それって英語で読んだの?」 |

|
「いやその、英語の反対のページの対訳で。」ーー; |

|
「意味ないじゃん!」 |

|
「。。。。」orz |
2009年05月14日 Posted by igoten at 07:27 │Comments(0) │読書
のぼうの城
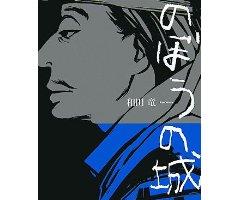 のぼうの城
のぼうの城和田 竜(著)
「BOOK」データベースより
時は乱世。天下統一を目指す秀吉の軍勢が唯一、落とせない城があった。 武州・忍城。周囲を湖で囲まれ、「浮城」と呼ばれていた。 城主・成田長親は、領民から「のぼう様」と呼ばれ、 泰然としている男。智も仁も勇もないが、しかし、誰も及ばぬ「人気」があった―。
時は乱世。天下統一を目指す秀吉の軍勢が唯一、落とせない城があった。 武州・忍城。周囲を湖で囲まれ、「浮城」と呼ばれていた。 城主・成田長親は、領民から「のぼう様」と呼ばれ、 泰然としている男。智も仁も勇もないが、しかし、誰も及ばぬ「人気」があった―。
小田原の北条氏を攻める日の出の勢いの秀吉、
その秀吉の筆頭家老ともいえる石田光成が
北条氏方支城の忍城を秀吉譲りの水攻めで攻める。
三成軍3万対する忍城方は兵わずか300。
そしてそれを率いるはでくのぼうと呼ばれる城主成田長親。
のぼうとはでくのぼうと言うところを遠慮して言っている言葉。
設定としては面白くないはずがない。
歴史的にもこの城は何と小田原城が落ちた後も、
開城を受け入れるまで三成軍の攻撃を撥ね返すのである。
さて「のぼうの城」であるが、読後ちょっと物足りさを感じさせる。
文章がどうのこうのと言うのではないが、主役の成田長親と
いう人物の書き込みに深みがない。
本来なら何か長親の逸話書きながら長親という人物を浮か
びあがらせ、普段はでくのぼうと呼ばれた長親がここ一番の
危機に際して、非凡なる能力を発揮し、圧倒的に優勢な三成軍を
まるで子供をあやすが如く翻弄する。
ここで読者は拍手喝采................
こうこなくっちゃ。
着想が面白いだけに惜しい。
まだ作者は若いのでこれからもっと良い物を書きそうな予感が。
山本周五郎に同じ忍城をテーマにした短編小説
「笄堀」(こうがいぼり)がある。
笄とはかんざしのようなものである。(違うかな)
これは留守の城主に代わってその妻女が三成軍に立ち向かう
というもので、女だてらに鎧を着込み陣頭指揮を取るために
座っているのだが、実は座っているのは妻女の娘で、
妻女は顔を隠して他の女人たちと堀を掘っているという
筋書きである。
さすがに「日本婦道記」の作者だけあって、感動、涙の絶品の
短編となっている。
更にこの小説は 「荒姫さま」という題名で出演原節子、監督黒澤明で
東宝から昭和20年に映画化されている、ぜひ観てみたいな。
「のぼうの城」も映画化の予定があるということで、主人公の
成田長親がどのような演出になるか楽しみなところである。
2009年05月13日 Posted by igoten at 07:33 │Comments(3) │読書
シュリーマン旅行記 清国・日本
 シュリーマン旅行記清国・日本
シュリーマン旅行記清国・日本
H.シュリーマン (著)
石井 和子 (翻訳)
「BOOK」データベースより
トロイア遺跡の発掘で知られるハインリッヒ・シュリーマン。 彼はその発掘に先立つ6年前、世界旅行の途中、中国につづいて 幕末の日本を訪れている。3ヵ月という短期間の滞在にもかかわらず、 江戸を中心とした当時の日本の様子を、なんの偏見にも捉われず、 清新かつ客観的に観察した。執拗なまでの探究心と旺盛な情熱で、 転換期日本の実像を生き生きと活写したシュリーマンの興味つきない見聞記。
トロイア遺跡の発掘で知られるハインリッヒ・シュリーマン。 彼はその発掘に先立つ6年前、世界旅行の途中、中国につづいて 幕末の日本を訪れている。3ヵ月という短期間の滞在にもかかわらず、 江戸を中心とした当時の日本の様子を、なんの偏見にも捉われず、 清新かつ客観的に観察した。執拗なまでの探究心と旺盛な情熱で、 転換期日本の実像を生き生きと活写したシュリーマンの興味つきない見聞記。
なんと驚いたことに、トロイの遺跡の発掘で知られるあのシュリーマンが
その発掘の6年前に、江戸か明治へと変わる3年前の日本に来ているのだ。
しかも素晴らしいことにシュリーマンはその時の日本の様子を克明に
記述していたのである。
この頃の欧米人は皆日本に対する憧れが有ったようだ。
次のような記述がある。
これまで方々の国でいろいろな旅行者に出会ったが、
彼らはみな感激しきった面持ちで日本について語ってくれた。
私はかねてから、この国を訪れたいという思いに身を焦が
していたのである。
次は日本での税関での記述である。
日曜日だったが、日本人はこの安息日を知らないので、
税関も開いていた。
二人の官吏がにこやかに近づいてきて、オハイヨと
云いながら、地面に届くほど頭を下げ、三〇秒もその
姿勢を続けた。
次に、中を吟味するから荷物を開けるようにと指示した。
荷物をとくとなると大仕事だ。
出来れば免除してもらいたいものだと、官吏に一分ずつ出した。
ところが何と彼らは、自分の胸を叩いて「ニッポンムスコ」
(日本男児?)と言い、これを拒んだ。
日本男児たるもの、心付けにつられ義務をないがしろにするは
尊厳にもとる、というのである。
おかげで私は荷物を開けなければならなくなったが、彼らは
言いがかりをつけるどころか、ほんの上辺だけの検査で満足してくれた。
お寺に関しては
境内に足を踏み入れるや、私はそこに漲る(みなぎる)このうえもない
秩序と清潔さに心を打たれた。大理石をふんだんに使い、ごてごて
と飾り立てた中国の寺は、きわめて不潔で、しかも頽廃的だったから、
嫌悪感しか感じなかったものだが、日本の寺は、鄙びたといっても
いいほど簡素な風情であるが、秩序が息づき、ねんごろな
手入れの跡も窺われ、聖域を訪れるたびに私は大きな歓びを
おぼえた。
(中略)
どの窓も清潔で、桟にはちりひとつない。老僧も子坊主も親切さと
この上ない清潔さがきわだっていて、無礼、尊大、下劣で汚らしい
シナの坊主たちとは好対照をなしている。
そして様々な江戸の風俗や景色生活様式を紹介している。
最後にこのように結論付けている。
もし文明という言葉が物質文明を指すなら、日本人は
きわめて文明化されていると答えるだろう。
なぜなら日本人は、工芸品において蒸気機関を使わずに
達することの最高の完成度に達しているからである。
それに教育はヨーロッパの文明国家以上に行き渡っている。
シナをも含めてアジアの他の国では女たちが完全な無知の
中に放置されているのに対して、日本では、男も女もみな
仮名と漢字で読み書きが出来る。
この後はキリスト教徒から見た体制の批判が続くのであるが。
この本は優れた観察能力を持つ西欧人が書いた世界有数の
教育を誇り、清潔で勤勉で誇り高い江戸末期の日本と日本人の
観察記録であり、我々日本人にとっては失ってしまった日本人の
美意識を後悔と共に思い出させてくれる貴重な記録書なのである。
2009年05月12日 Posted by igoten at 16:09 │Comments(0) │読書
トンデモWEB業界
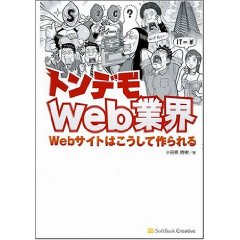 トンデモWeb業界
トンデモWeb業界 小田原 貴樹 (著)
「BOOK」データベースより
ファンタジーな顧客、奇行に走る経営者、下手なデザイナー、トンズラするプログラマー。 一見華やかなWeb業界の裏側で日々繰り広げられるWebサイト構築現場のドタバタ劇。
ファンタジーな顧客、奇行に走る経営者、下手なデザイナー、トンズラするプログラマー。 一見華やかなWeb業界の裏側で日々繰り広げられるWebサイト構築現場のドタバタ劇。
Web業界で10年間働いていた筆者がその裏側で
繰り広げられるドタバタを、ユーモアを交えて紹介
している本である。
実はこの本インターネットの「@IT」と言うところに
連載されていたものであるが、本になったということで
あわてて購入した。
この本ところどころにお客さんや、他のWEB技術者との
会話が織り込まれており、その会話がめちゃくちゃ面白い。
特にWEB関係に携わった人にはたまらないだろう。
(私はWEB関係に携わったことはないのだが)
客との会話。
「ぜ、全世界に商品を販売するということは、英語版も作るんですか?」
「いや、作らないよ。そんな予算もないし。でも、
全世界につながってるんでしょ?インターネットって」
「ええ、全世界につながっています」
「すごいじゃない!。ということは全世界でも売れるということでしょ?
あれ、なんていうか『グローバル・スタンダード』だっけ?」
「いえ、普通に『ワールド・ワイド』だと思います。」
自分の父親との会話である。
「ITゆうのは、ええのぉ。もらった金の全部がもうけじゃろうが」
「そんなことはないよ」
「なんでや、材料がいるわけじゃあるまぁが」
「材料はいらんが、回線代とか設備とかいろいろ金がかかるんよ」
「そんなもん、うちでもかかるわぁや」
「いやその割合が大きいんよ」
「そんなの関係あるかぁや、おまえの自己管理ができとらんけぇ、
金がないんだよ」
「まあその部分はそうかもしれんけどね........]
(ちなみに両親はラーメン屋をやっているとのこと)
こんなのが初めから終わりまで書かれている。
これを読むとWEB業界だけは入りたくないなというか、
こんなに面白いなら一度入ってみたいというか.......
おもしろうてやがて悲しき鵜舟かな 芭蕉