知足
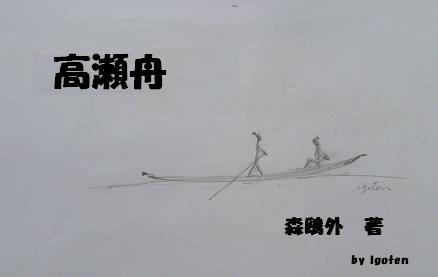
まずこの表紙どうであろうか?
私ならこんな表紙にするが。
この小説を初めて読んだのは、
息子が中学3年生の時で、なにげなく息子の
国語の本をパラパラめくっていたら、この小説が
載っていた。
高瀬舟は罪人を運ぶ船底の平らな木造船である。
この物語は護送の役目の同心・羽田庄兵衛が喜助と言う
罪人を護送中に喜助がいかにも晴れやかな顔をしている事を
不審に思ったことから始まる。
極貧に喘いでいた喜助は、島送りになったら食べさせてもらえる上に
鳥目200文を頂戴して有難いと言う。
喜助の犯した罪は自殺を図って死にきれず苦しんでいる弟に
手を貸し死なせてやったということだった。
この小説はいわゆる「知足」と言うことと、「安楽死」と
言うことをテーマにしている。
「知足」とは吾唯知足(われただたるをしる)と言う釈尊の
言葉であり、人は欲望を無限に膨らませてはならないという教えである。
2年位前までTBS系で『ウルルン滞在記』と言う番組をやっていた。
私はこの番組が好きでよくみていたいたが、何も持たず
ただ大家族だけの原住民が、本当に幸せそうね暮らしていた。
あれが『知足』であろう。
一方、有り余るほどの『物』に囲まれていても、一向に心は休まらず、
ただ明日への不安だけを募らせている日本人。
持っても、持ってもまだ持ちたいという餓鬼のような無限地獄に、
日本人はいつから陥ってしまったのかな。
『知足』という言葉に一番遠い国がアメリカ、次が日本そしてそれを
中国がものすごい速度で追いかけている、そんな気がする。
『安楽死』に関してはさすが森鴎外は医者だけあって、当時から 問題意識を持っていたのだろう。
この物語に登場する喜助が、弟を殺したという罪の意識を 全く持っていない所に、森鴎外自身の安楽死に対する考え方の 一端が見える。
森鴎外の文は旧仮名使いで少し読みにくいところはあるが
素晴らしい美文である。
其日は暮方から風が歇(や)んで、空一面を蔽つた薄い雲が
月の輪廓をかすませ、やうやう近寄つて來る夏の温さが
兩岸の土からも、川床の土からも、靄になつて
立ち昇るかと思はれる夜であつた。
更にこの小説の最後の文章も素晴らしい文である。
次第に更けて行く朧夜に、沈默の人二人を載せた高瀬舟は、
黒い水の面をすべつて行つた。
黒い水の面をすべつて行つた。
いずれにしろこの作品はゆっくり読めば読むほど
心の中に染み込んでいくような名作である。
この小説を読みたい方は、 『高瀬舟 』をどうぞ。





